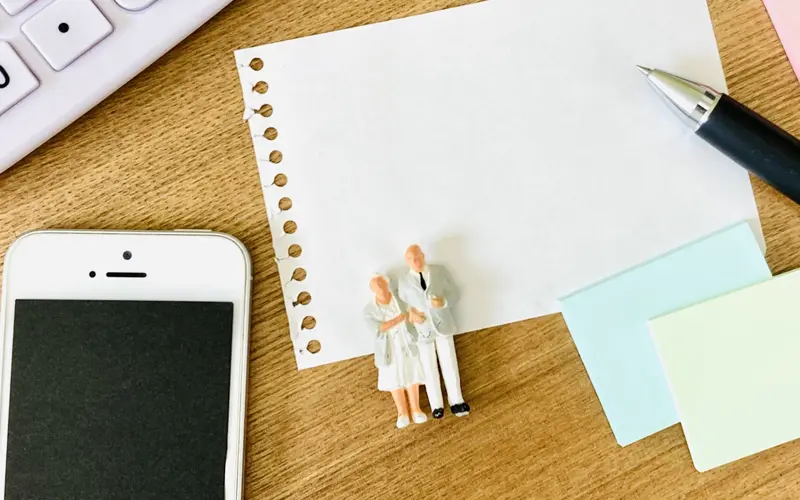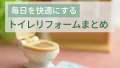日本はいま、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。2025年には人口の約30%が65歳以上となり、介護や医療、生活支援など社会全体の負担がますます増大していくことが予想されています。高齢者が安心して暮らし続けられる社会を実現するには、従来の仕組みだけでは対応が難しく、新たな発想と技術の力が求められています。
そこで注目されているのが「AgeTech(エイジテック)」という分野です。
AgeTechとは、高齢者の生活の質(QOL)を高め、健康維持や自立を支援するためのテクノロジー全般を指します。AI(人工知能)を活用した健康管理アプリ、介護ロボット、遠隔医療サービス、スマート家電、VR(仮想現実)を使ったリハビリ支援など、さまざまな技術がすでに現場で活用されはじめています。
こうした技術は、高齢者本人の快適な暮らしに貢献するだけでなく、家族や介護従事者の負担軽減、社会全体の生産性向上にもつながるものです。
今回はAgeTechの最新動向と注目されている技術分野、国内外の先進事例、そして今後の課題と展望について、わかりやすくご紹介していきます。未来の高齢化社会に向けたヒントを、一緒に探っていきましょう。
AgeTechとは何か?

AgeTech(エイジテック)は、「Aging(加齢・高齢化)」と「Technology(技術)」を組み合わせた言葉で、高齢者の生活や健康をサポートするテクノロジーの総称です。医療や介護の分野にとどまらず、日常生活、移動、社会参加、コミュニケーションまで、幅広い領域で活用が進んでいます。
背景にあるのは、世界的な高齢化の加速と、それに伴う人手不足や社会保障負担の増大といった課題です。これまで主に人の力に頼ってきた介護や生活支援の現場に、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ロボティクス、ウェアラブルデバイス、VR/AR(仮想・拡張現実)といった先端技術が次々と導入されつつあります。
健康状態を見守るスマートウォッチ、転倒リスクを減らす見守りセンサー、自動運転車両による移動支援、VRによる仮想旅行などがその一例です。こうしたAgeTechは、高齢者本人の自立と安心を支え、同時に家族や介護スタッフの負担軽減にも貢献しています。
今後は、より多くの人が使いやすいデザインやコストの低下が進むことで、一般家庭にもさらに広がっていくと期待されています。
最新AgeTech動向と注目されている分野
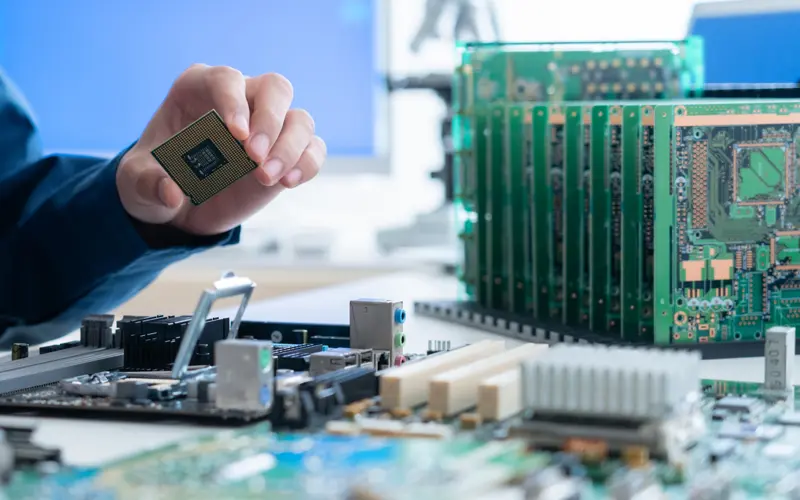
AgeTechの対象は多岐にわたりますが、現在特に注目されているのは「健康・医療」「介護・生活支援」「移動支援」「社会参加・孤立防止」の4つの分野です。それぞれの最新動向と具体的な取り組みを見ていきましょう。
1.ヘルスケア・医療分野
高齢化の進行とともに、医療機関へのアクセスや継続的な健康管理が大きな課題となっています。こうした背景から、遠隔医療やウェアラブルデバイス、AIによる診断支援といったテクノロジーが急速に普及し始めています。
スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを活用すれば、心拍数や血圧、血中酸素濃度、歩数といった日々の健康データを自動的に記録できます。Appleの「Apple Watch」は心電図(ECG)や転倒検出機能を備えており、緊急時には自動で家族や救急サービスに通知することも可能です。
- 予防医療の促進:日常の健康データが蓄積され、生活習慣病の予兆管理が可能に
- 高齢者向け専用デバイスの登場:心電図機能付きの高齢者向けスマートウォッチ(Oura RingやWithings ScanWatch Horizonなど)
- AI診断の次の段階:画像診断だけでなく、音声解析による認知症スクリーニングも研究中(国立精神・神経医療研究センターなど)
オンライン診療サービスの普及も加速中です。「CLINICS(クリニクス)」などのサービスを利用すれば、スマホやタブレットを通じて医師の診察を受けられ、処方箋も自宅まで郵送してもらえるケースもあります。これにより、通院が困難な高齢者の負担が大幅に軽減されています。
さらに、AIを活用した診断支援も現場に浸透しつつあります。「エルピクセル社のEIRL(エイル)」という画像診断AIは、脳動脈瘤や肺疾患の発見をサポートし、医師の負担軽減と診断精度の向上に貢献しています。認知症の早期発見にAIを活用する取り組みも進んでおり、今後は家庭レベルでもこうした支援ツールが身近になると期待されています。
2.介護支援・生活支援分野
介護人材不足は日本の介護現場が抱える大きな課題です。そのため、介護支援ロボットやスマートホーム技術の導入が進められています。これらは高齢者の自立を助けるとともに、介護スタッフや家族の負担を軽減する効果があります。
代表例としては、パナソニックの「リショーネPlus」というベッド型介護ロボットがあります。これはベッドがそのまま車いすの形状に変形し、移乗介助の負担を大きく減らせる画期的な製品です。
また、見守りセンサーの導入も拡大中です。パラマウントベッドの「眠りSCAN」は、マットレスの下にセンサーを設置するだけで睡眠状態や呼吸・心拍数を自動モニタリングできます。夜間の見守り業務が軽減され、スタッフの労働環境改善につながっています。
- ケアの見える化:介護記録がデータ化されることで施設間や家族間で情報共有が容易に
- IoT連携の進展:眠りSCANなどのセンサーがナースコールやスマート家電と連携
- 高齢者向けスマートホーム市場の拡大:大手家電メーカーが高齢者対応製品を次々投入中(例:パナソニックの音声操作テレビなど)
スマートスピーカーも高齢者の生活を支える身近な存在になりつつあります。Amazonの「Echoシリーズ」やGoogleの「Nest Hub」を使えば、音声で家電を操作したり、服薬時間のリマインダーを設定したりできます。画面付きのモデルならビデオ通話機能も利用可能で、離れて暮らす家族とのつながりを維持することもできます。
介護記録のデジタル化も進んでおり、「まもるくん」や「ほのぼのNEXT」といった介護記録ソフトが現場で活用されています。音声入力やタブレット対応により、スタッフの記録業務が効率化し、より多くの時間を直接ケアに充てられるようになっています。
3.移動支援・交通分野
移動の自由は高齢者の生活の質(QOL)に大きく関わる要素です。しかし、加齢に伴う身体機能の低下や運転免許の返納などにより、移動の選択肢が限られてしまうケースも少なくありません。こうした中、全国各地で自動運転車両の実証実験が行われています。
茨城県境町では、町内のコミュニティバスとしてNavya(ナビヤ)社製の自動運転バスが運行中。住民の買い物や通院の足として利用されています。
また、パーソナルモビリティの分野でも革新が進んでいます。WHILL社の「WHILL Model C2」は、電動車いすとパーソナルモビリティの中間のようなデザインで、従来の車いすよりもスタイリッシュで取り回しが良く、買い物や外出時にも活躍しています。
さらに、公共交通機関における高齢者向け支援アプリも登場しています。京王電鉄の「バスナビ」は、バスの接近情報だけでなく、優先座席の空き状況や車両の混雑度なども提供予定です。今後は階段回避ルートの案内やエレベーターの利用可否情報など、よりきめ細かい機能が期待されています。
- 自動運転とMaaS(Mobility as a Service)の融合が進行
- パーソナルモビリティが貸与サービス化(例:自治体が電動カート貸出)
- 移動弱者対策アプリにAIが組み込まれ、個別化された移動支援提案が可能に(京王電鉄や東京メトロの実証)
4.孤立防止・社会参加支援分野
社会的孤立や孤独は、高齢者の心身の健康に悪影響を与えることが知られています。AgeTechはこの課題に対し、新しい技術と発想で解決策を提供しはじめています。
NECの「離れていても、いっしょ。」というサービスは、タブレット端末を活用し、家族との写真や動画の共有を簡単に実現。操作はワンタッチで済み、ITに不慣れな高齢者でも使いやすい点が特徴です。
Synamon社の「NEUTRANS(ニュートランス)」では、VRプラットフォーム上で旅行体験や交流イベントが提供されており、施設入所中の高齢者でも仮想空間を通じて新たな体験やつながりを楽しむことが可能です。
大阪府豊中市の「みまもりあいプロジェクト」は、地域住民が互いに見守りネットワークを築き、情報共有や助け合いの場をデジタル上に設けています。これにより、高齢者が地域との関係性を維持し、安心して暮らせる環境が整えられています。
- VR活用が拡大:脳トレや回想法にVRが活用され、ANAやJTBの旅行体験コンテンツは高齢者施設でも導入実績あり。認知機能や生活意欲の向上が期待されている。
- 高齢者向けSNSの登場:おしるこなどの高齢者向けSNSは、簡単な操作で写真やメッセージのやり取りが可能。安全なクローズド環境が安心感を生み、利用者が増加中。
- 地域DX化の進展:自治体がLINEを活用した高齢者向け情報配信を積極展開。防災情報や地域イベント案内、健康啓発など、生活に役立つ情報が直接届く仕組みが普及している。
- AIチャットボットの活用:会話型AIチャットボットが介護施設や家庭で試験導入され、孤独感の軽減や日常的な会話の促進に効果を発揮。英国など海外では一般家庭での普及が進んでおり、日本でも今後活用が期待される。
- 趣味・学び直し支援のデジタル化:生涯学習プラットフォーム「まなびの窓」などにより、高齢者がオンライン講座や趣味活動に参加する機会が広がっている。知的好奇心や社会参加意欲の維持に寄与。
グローバル視点で読み解く、暮らしを変えるAgeTech事例集

世界各国で進むAgeTechの導入。文化や社会制度の違いによってアプローチは多彩ですが、どの国でも目指しているのは「高齢者がより豊かに暮らせる社会」です。
日本の現場でも独自の工夫が光る事例が数多く生まれています。ここでは、海外と日本それぞれの注目事例をいくつか紹介しましょう。
世界のAgeTechは今どう進んでいる? ~暮らしを変える海外の取り組み~
英国では、NHS(国民保健サービス)が全国規模で遠隔医療とAI診断支援を導入し、医療アクセスの地域格差解消に取り組んでいます。
北欧のスウェーデンでは自治体がスマートホーム技術を積極導入。高齢者が自宅で安全かつ快適に暮らせるよう、家電や見守りシステムが生活環境に組み込まれています。
米国では孤独解消AIロボット「ElliQ」が注目を集めています。家庭内に設置することで日常の会話や健康リマインダーを提供し、高齢者の社会的なつながり感をサポートしています。
GoGoGrandparentという配車サービスは、スマホが苦手な高齢者向けに電話一本でUberやLyftが利用できる仕組みを整えており、高齢者の移動の自由を広げています。
海外ではこうした事例が公共サービスや医療制度とも積極的に連携しながら発展しているのが特徴です。
海外のAgeTech活用の主なシーンと特徴
| 主なシーン | 主な事例・取り組み | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 健康管理・医療アクセス | 英国NHSによるAI診断支援・遠隔医療の全国展開 | 公的医療制度との統合/全国規模での平等なアクセス |
| 自宅での安心な暮らし | スウェーデン自治体によるスマートホーム技術導入 | 高齢者が自宅で安心して生活できる環境を構築 |
| 日常のつながりと交流 | 米国ElliQ(AIロボットによる会話・健康支援) | AIが日常会話・健康管理をサポート、家庭内で普及 |
| 移動と外出の自由 | 米国GoGoGrandparent(スマホ不要で配車サービス利用) | 高齢者に優しいUX(電話一本でサービス利用可能) |
| 地域ぐるみの見守りと支援 | 欧州諸国での公共サービスとAgeTechの制度的な連携(例:遠隔医療、見守り) | 公共部門がAgeTechを積極採用/国策として推進 |
日本各地で広がる、暮らしを変えるAgeTechの取り組み
国内でもさまざまな形でAgeTechが実装されつつあります。パナソニックは介護支援ロボットやベッド一体型の移乗支援製品を展開し、介護現場の負担軽減に貢献しています。
交通分野では、茨城県境町が自動運転バスを地域交通に組み込み、通院や買い物などの日常の移動支援を実現しています。
都市部と地方の両方で進んでいるのがスマートスピーカーや見守りIoTの導入です。家族とのつながりを維持しつつ、自宅内での安心・安全な生活を支援する取り組みが広がっています。
地方銀行や通信会社との連携による地域見守りサービスも全国で導入が進行中。金融インフラや通信インフラを活用した地域密着型の高齢者支援モデルが、日本ならではの形で進化しています。
日本ではこうした現場の知恵や地域密着の工夫がAgeTech導入の推進力となっています。
日本のAgeTech活用の主なシーンと特徴
| 暮らしの場面 | 主な事例・取り組み | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 介護の現場支援 | パナソニックの移乗支援ロボット・介護支援製品 | 介護現場のニーズに根ざした現場発の技術適用 |
| 移動と地域交通の支援 | 茨城県境町の自動運転バス導入 | 地方の高齢者の移動支援にスマート交通を活用 |
| 自宅での見守りと快適な生活 | スマートスピーカー/見守りセンサー導入(大手企業・自治体連携) | 家庭内で高齢者の安全・快適な生活を支援 |
| 地域ぐるみの見守りと交流 | 地方銀行/通信会社と連携した見守りサービス(例:ゆうちょ銀行など) | 地域資源を活用した地域密着型AgeTechモデルが広がる |
| 家族とのつながり維持 | NEC「離れていても、いっしょ。」サービス | 家族の安心感向上と高齢者の社会的孤立防止を両立 |
国や地域によって文化や制度の違いはありますが、「高齢者が自分らしく暮らすこと」という目標は世界共通です。日本独自の強みや現場の工夫も、世界の知恵に学びつつさらに進化していくことが期待されます。
AgeTech普及のカギは何か? 今抱える課題と解決のヒント

AgeTechはさまざまな分野で実用段階に入りつつありますが、普及が一気に広がるためにはまだいくつかの壁があります。現在見えている主な課題と、それに対する解決の方向性について考えてみましょう。
課題①:使いやすさと心理的な壁
AgeTechの活用が進む中で、意外なほど大きな壁になるのが「操作の難しさ」や「心理的な抵抗感」です。
スマートスピーカーやウェアラブルデバイス、介護ロボットなど便利なツールは数多く登場していますが、それらを高齢者自身が「使いこなせる」と感じるまでにはギャップがあります。
初めて使うデバイスに対して「壊してしまいそう」「ボタンが多くてわかりにくい」「設定が難しい」と感じるケースは少なくありません。また「自分には新しい技術は必要ない」「家族や介護スタッフが使えば十分」といった心理的な距離感も存在します。
こうした壁を乗り越えるには、まず高齢者の目線に立った「参加型デザイン」が欠かせません。製品開発段階から高齢者の声を取り入れ、操作が直感的でシンプルな設計にすることが重要です。
音声やジェスチャーによる操作は、その点で非常に有望な手法です。ボタン操作よりも自然な形で使えるため、技術の壁を感じにくくなります。さらに、最初に成功体験を積めることも大切です。「一度やってみたら意外と簡単だった」という経験が、AgeTechへの心理的な扉を開いてくれます。そのため、導入時のサポートや使い始めの練習機会を設けることが普及促進のカギになるでしょう。
課題②:デジタル格差と教育不足
もう一つ大きな課題はデジタル格差です。
現在の高齢者層は、若年層に比べてIT機器に慣れていない方が多く、スマホやインターネットそのものの利用率にも地域や所得によって差があります。都市部の比較的高所得層ではスマホが当たり前のように使われていますが、地方や低所得層ではガラケーや固定電話中心の生活が今なお多く見られます。
こうした状況では、いくら優れたAgeTechが存在しても、それを活用するリテラシーが整わなければ普及は限定的になってしまいます。家族との同居状況にも左右されやすく、孤立しがちな高齢者ほど新しい技術の恩恵を受けにくいという矛盾が生じがちです。
この課題への対応としては、行政や地域による教育機会の整備が不可欠です。自治体が主催するスマホ講座やデジタル活用教室、公共施設での「使い方相談窓口」などは、今後さらに広げていくべき取り組みです。
また、家族や地域住民が積極的に世代間サポートを行うことも効果的です。孫世代が祖父母に使い方を教えたり、自治会などの活動で「みんなで試してみよう」という雰囲気をつくることで、高齢者のデジタル活用意欲は大きく変わってきます。
こうした地域ぐるみの支援体制づくりが、デジタル格差の解消に向けた現実的な道筋になるでしょう。
課題③:コストと持続可能性
AgeTechの普及において、コストの問題は避けて通れません。
最新の介護ロボットや高性能な見守りシステム、スマートホーム機器は便利で効果も高いものの、初期費用や維持コストが高額なケースが多く、結果的に一部の家庭や施設でしか導入が進まないという状況があります。
特に在宅介護や一人暮らしの高齢者にとって、数十万円単位の設備投資は大きな負担です。また、利用料やサービス継続費用(サブスクリプション型)も普及の妨げになる要素のひとつです。
この課題に対する解決策のひとつが、リースやレンタルの仕組みの充実です。短期間から試用でき、費用の負担感が抑えられれば、より多くの家庭でAgeTechの導入が現実的になります。価格の多様化も必要です。プレミアム機能を備えた高額モデルだけでなく、必要最低限の機能に絞ったシンプルで低価格な選択肢が求められます。そのためにはメーカー側の製品ラインナップ工夫とともに、行政の介護保険制度や公的補助制度との連携が不可欠です。
AgeTechが「特別なもの」ではなく、「普通の家庭で当たり前に使われるもの」になるために、制度面からの支援も今後ますます重要になっていくでしょう。
まとめ:高齢化社会とともに育つAgeTechの可能性

AgeTechは今、進化の途上にあります。技術そのものは急速に発展していますが、誰もが無理なく使いこなし、暮らしの中で自然に活かせる社会には、まだ向かうべき道があります。
一方で、課題の解決や新しい取り組みは着実に進んでいます。高齢社会という現実と向き合いながら、AgeTechもまたその社会とともに成長し、形を変えていくのだと思います。
大切なのは、技術が人を支える道具であることを忘れないこと。使う人の視点を大切にしながら、AgeTechがより多くの人の暮らしを豊かにしていく未来を、これからも見守り、育てていきたいものです。
※上記記事は2025年6月7日時点のものです。
※記事内で取り上げた商品・サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
※当サイトに掲載された情報については、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。