かつては「未来の話」だったスマート社会が、今や私たちの暮らしのすぐそばに迫っています。日本が掲げる「Society5.0(ソサエティ・ファイブ・ポイント・ゼロ)」は、AIやIoT、ロボティクスなどの先端技術を使って、人間中心の社会を築こうという国家的な構想です。
とはいえ、「超スマート社会」と聞いてもイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか?
「最新技術」という言葉は華やかに響きますが、Society5.0の本質は技術そのものではなく、私たち一人ひとりの暮らしをより良くすることにあります。
今回は、難しい言葉や専門用語をなるべく使わずに、生活者の視点からSociety5.0の世界をご紹介します。
すでに始まっている事例を知ることで、あなた自身の暮らしにもどんな変化が訪れるのか、きっとイメージが膨らむはずです。
Society5.0とは? ~超スマート社会の基本をやさしく解説~

Society1.0から5.0までの流れ
私たちの社会は、長い時間をかけて少しずつ進化してきました。いま日本が掲げる「Society5.0」は、この進化の「次のステージ」を表しています。
簡単に歴史を振り返ってみましょう。
| 社会のステージ | 時代背景・技術 | 社会の特徴・暮らしの変化 |
|---|---|---|
| Society1.0 | 狩猟社会/原始時代 | 人は自然の中で生活。獲物を追い、食料は自給。移動生活が中心。集団生活は小規模で自給自足が基本。 |
| Society2.0 | 農耕社会/約1万年前~ | 農業が発展し、定住生活が始まる。集落や村落が生まれ、余剰生産が可能に。文字や通貨の誕生により、文化や経済活動が発展。 |
| Society3.0 | 工業社会/18世紀~産業革命 | 機械化・大量生産が社会を変革。都市化が進行し、鉄道・電力・近代インフラが整備される。物質的な豊かさが急速に向上。 |
| Society4.0 | 情報社会/20世紀後半~ | コンピュータ・インターネット・モバイルデバイスの普及。情報が瞬時に世界中に行き渡る。知識労働やサービス業が経済の中心に。 |
| Society5.0 | 超スマート社会/現在~ | AI・IoT・ロボティクス・ビッグデータなどの活用が進む。サイバー空間と現実空間が融合。社会課題の解決(高齢化・地域格差・環境問題)を目指す、人間中心の社会へと進化。暮らしはよりパーソナライズされ、安心・快適に。 |
こうして見ると、Society5.0は単なる「テクノロジー社会」ではなく、社会全体が人々の幸福や課題解決に向けて進化する段階であることがわかります。
今までは便利なサービスを受け取るだけだった私たちが、社会の一員として新しい価値を共に作り出す時代とも言えるでしょう。
Society5.0が暮らしに与える影響とは
それでは、Society5.0の進化は、私たちの毎日の暮らしにどんな影響を与えるのでしょうか?
キーワードは「人間中心の社会」と「リアルとデジタルの融合」です。
これからの社会では、AIやロボット、ビッグデータ、IoTなどの技術が自然に生活の中に組み込まれ、誰もが便利で安心して暮らせる社会を目指します。その結果、今まで不便だったことが解消されたり、社会全体がもっと包摂的(インクルーシブ)な方向へと進んでいきます。
たとえば、こんな変化が見えてきています。
高齢者や子育て世代のサポートが進化する
AI見守りサービスや介護ロボットが自宅での安心を提供。子供の登下校や位置情報も家族が把握でき、家族全員の安心感が向上します。
移動がもっと自由で快適に
MaaS(Mobility as a Service)により、電車・バス・シェアサイクルなどの移動手段を一括で予約・決済。免許返納後の高齢者でも自由な外出が可能に。
働き方がもっと柔軟になる
リモートワークやクラウドツールが進化し、地方に住んでいても都市部と同じような働き方が可能。自分らしいライフスタイルが選べるようになります。
買い物や食生活がスマートに
スマート冷蔵庫が食材の在庫を管理して不足品を提案。地産地消の食品がアプリで手軽に購入可能に。食の安全性や健康意識が高まる生活へ。
地域とのつながりが深まる
地域SNSやデジタル地域通貨を通じて、住民同士の交流が活性化。若者から高齢者まで地域に参加する機会が増え、孤立を防止します。
社会課題解決に市民が参加できる
スマートシティの実証実験や市民参加型のエネルギー管理など、一人ひとりが社会づくりに貢献する場面が増えています。
このように、Society5.0は私たちの生活のあらゆる場面に影響を及ぼしていきます。「特別な人だけが恩恵を受ける世界」ではなく、誰もが自然に技術の恩恵を感じられる社会を目指しているのです。
そしてその変化は、もう未来の話ではありません。すでに日本各地でさまざまな取り組みが始まっており、私たちの暮らしの中にも少しずつ入り込んできているのです。
ケース①「生活を見守るスマートな安心・安全サービス」
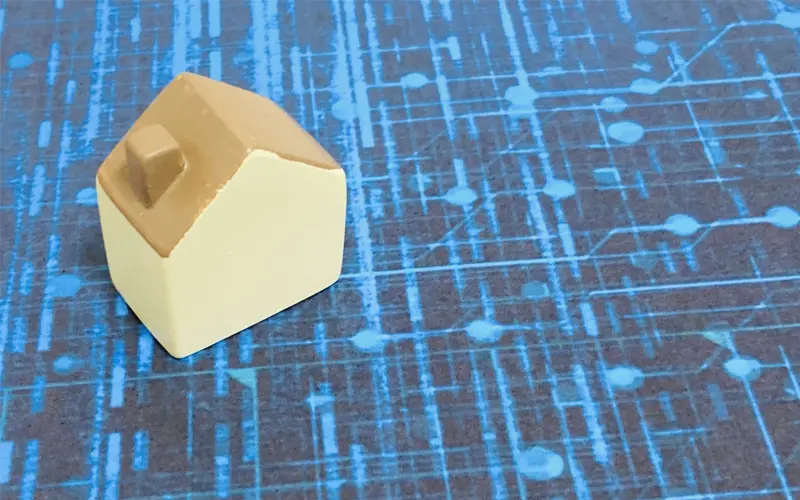
家族が健やかに過ごせる環境づくり、防犯や防災の備え、高齢者や子どもを支える見守りの仕組み…など、安全と安心はどの世代・どんな地域でも大切な価値です。こうした分野では今、AIやIoTなどの先端技術が着実に導入され、社会全体の安心感を高める動きが進んでいます。
例えば、センサーやカメラを活用して異常を早期に検知したり、スマホアプリを通じて災害情報を迅速に届けたりと、これまでよりも高度なサポートが一般家庭や地域レベルでも手軽に利用できるようになってきました。
また、防犯や防災といった従来は「備えの分野」と考えられていたものが、日常生活の一部として自然に取り入れられつつあるのも大きな変化です。今や特別な設備投資や専門知識がなくても、家庭用の見守り機器やスマートフォンアプリを通じて誰でも安心を得られる選択肢が増えています。
今回は高齢者や子どもを支える見守りサービス、地域社会を守るスマート防犯、そして災害への備えを支える最新のスマート防災の事例をご紹介します。今後、こうした取り組みはさらに普及し、一人ひとりの生活の中に自然と組み込まれていくでしょう。
高齢者や子どもを見守るスマートサービス
まもりホットライン(KDDI・NTTドコモ)
高齢者の位置情報や体調データ、日常の行動履歴をスマホで確認できる見守りサービス。専用端末やスマートウォッチ型のデバイスを身につけるだけで、家族はスマホアプリを通じて大切な家族の様子を把握できます。
遠方に住んでいる家族でも安心感を得られる/緊急時の通知機能により迅速な対応が可能。
coconavi(NTTドコモ)
子ども向けGPS端末を活用した登下校時の見守りサービス。子どもがGPS端末をランドセルなどに入れて持ち歩くことで、保護者はリアルタイムで位置情報を確認できます。学校や学童への到着・出発通知も設定可能。
子どもの現在地を手軽に確認できる/子ども自身の安心感も向上。
スマート見守り家電(SwitchBot、パナソニック系)
ドアや窓の開閉センサー、動きセンサーを活用した見守り家電。室内での異常な動き(例:通常は動いている時間帯に動きがない、ドアの異常開閉)が検知されると、スマホに通知が届きます。
室内の異常や事故リスクを早期に察知/高齢者の一人暮らしにも有効。
スマートウォッチ × 見守りサービス(Apple Watch、Fitbit+見守りアプリ連携)
スマートウォッチと見守りアプリを組み合わせた健康見守りサービス。心拍数や転倒検知機能を活用し、異常時は家族や介護者に即時通知が送られます。緊急SOS発信機能も搭載。
外出先でも健康状態の異常を即座に家族が把握できる/本人の安心感も高まる。
自治体 × 見守りIoT導入事例(神戸市、川崎市など)
自治体と民間が連携してIoTセンサーを活用した地域見守りを実施。住宅や公共施設に設置されたセンサーが住民の生活状況を把握し、異常があった場合は家族や自治体が迅速に対応できる仕組みが整いつつあります。
行政・家族・地域が一体となって高齢者を支える新しい仕組みが生まれている。
街を守るスマート防犯の最新動向
AI防犯カメラ「Safie」
クラウド型のAI防犯カメラシステム。店舗や公共スペースに設置されたカメラが不審な行動を自動で検知し、リアルタイムで通知。映像はクラウドに保存され、後から確認・分析も可能。
犯罪抑止力が高まり、地域全体の安全性が向上/店舗オーナーの防犯負担も軽減。
スマート玄関ロック(Qrio Lock、SwitchBotロック)
スマホアプリで施錠・解錠ができるスマートロック。自宅の玄関ドアに後付けでき、スマホで操作可能。家族の帰宅状況を確認でき、鍵の閉め忘れ防止にも役立ちます。
家族の安全確認が簡単にできる/鍵の紛失リスクが低減し、防犯意識が高まる。
街ぐるみの防犯ネットワーク(自治体・商店街のAIカメラ共同利用例)
地域ぐるみでAIカメラを共同運用する取り組み。商店街や自治体単位で防犯カメラ映像を共有し、不審者情報を迅速にやりとり。街全体の防犯意識が向上し、犯罪の未然防止に貢献しています。
地域全体の安心感が高まり、住民同士の協力意識が強まる。
災害への備えとスマート防災の進化
さくらインターネット × IoT防災センサー
河川水位や地震、土砂災害リスクをIoTセンサーで常時モニタリング。異常が検知されると住民にスマホ通知が送られ、自治体の対応も迅速化を図ることができます。
災害の早期避難判断が可能になり、被害を軽減できる。
スマホアプリ「Yahoo!防災速報」「Safety tips」
災害情報をリアルタイムで通知する防災アプリ。地震・津波・台風などの最新情報を多言語で配信。外国人観光客や在住者向けにも有効です。
最新の防災情報を誰でも即時に把握/避難行動の判断に役立つ。
自治体との連携型スマート防災マップ
地域の避難所情報やバリアフリー情報を反映したスマート防災マップ。AIが個別の状況(高齢者・障害のある方など)に応じて最適な避難ルートを提案する実証事例も登場中。
多様な人々が安全な避難行動を取りやすくなる/地域全体の防災力が向上。
安心・安全が“当たり前”になる未来へ
安全・安心のニーズは、これからのスマート社会の中でも重要なテーマの一つです。AIやIoTの活用により、見守りや防犯、防災の取り組みはますます高度化・普及しつつあります。
こうしたサービスは、特別な操作や設備を必要とせず、誰もが自然に取り入れやすい形で広がっているのが大きな特徴です。今後もこの流れは進み、より多くの人々が安心して毎日を過ごせる環境づくりが期待されます。
ケース②「日常をアップデートするスマートサービス」

スマートフォンや音声アシスタント、IoT家電、パーソナルAIなど、日々の生活を支えるテクノロジーは急速に進化しています。
こうした技術は単に「便利さ」を提供するだけではなく、一人ひとりの時間やエネルギーを節約し、より豊かな体験を生み出す方向に進化しつつあります。
さらに、移動手段や健康管理、教育といった分野でもパーソナライズされたサービスが当たり前に使われる時代が到来しています。家庭や外出先、日常生活の中で活用されているスマート技術の最新事例をご紹介します。
スマート家電と音声アシスタント活用
SwitchBotスマート家電シリーズ
既存の家電製品をスマート化する後付けデバイス。カーテン、照明、エアコンなどをSwitchBotでコントロールでき、スマホアプリや音声操作で自宅内の環境を自在に調整可能です。
毎日の生活動線がスムーズになり、わずかな動作負担が減る/高齢者や身体的な負担を感じやすい方にも有効。
Amazon Alexa/Google Nest Hub
音声アシスタントが家事・情報収集・娯楽のパートナーに。ニュースや天気予報の読み上げ、音楽再生、スマート家電操作、リマインダー設定などが音声だけで行えます。高齢者のサポート用途や子どもの教育支援にも応用事例が広がっています。
両手がふさがっている時でも家電や情報操作が可能/音声のみで日常生活の効率が上がる。
MaaS(モビリティ革命)で移動がもっと便利に
小田急MaaS「EMot」
電車、バス、シェアサイクル、タクシーなどの公共交通手段を一括検索・予約・決済できるアプリ。地域交通の利便性が大幅に向上し、観光客や高齢者、子育て世代にも喜ばれるサービスです。
移動の計画が簡単になり、公共交通の利用頻度が高まる/免許返納後の高齢者層にも有用なサポートツール。
東急「のるるんMaaS」
東急電鉄エリアで展開されているMaaSサービス。電車・バス・シェアサイクル・カーシェアを統合し、エリア内の移動がスムーズに。観光モデルルート提案やチケットの一括購入など、観光と地域利用の両方に対応できます。
複数の交通手段を一つのサービスで完結/観光客や子育てファミリー層の利便性が向上。
仙台市「Sendai MaaS」
仙台市が官民連携で推進するMaaS実証事業。電車・地下鉄・バス・タクシーに加え、観光地の入場券・飲食店クーポンもセット販売する独自の仕組み。交通と観光を一体的に体験できるモデルとして注目されています。
地域経済の活性化と観光体験の向上を両立/高齢者層の「おでかけ需要」喚起にも効果的。
生活の質を高めるスマートテクノロジー
一人ひとりの「便利さ」や「快適さ」は、スマート技術によって新たな次元に進化しています。これらのサービスは特別な人だけが使うものではなく、誰にとっても自然に利用できるものとして社会に浸透し始めています。
今後も、移動や健康、教育といった分野でさらに進化が加速し、日常の質を高める選択肢はますます広がっていくでしょう。
ケース③「地域をもっと身近にするコミュニティ型の最新サービス」
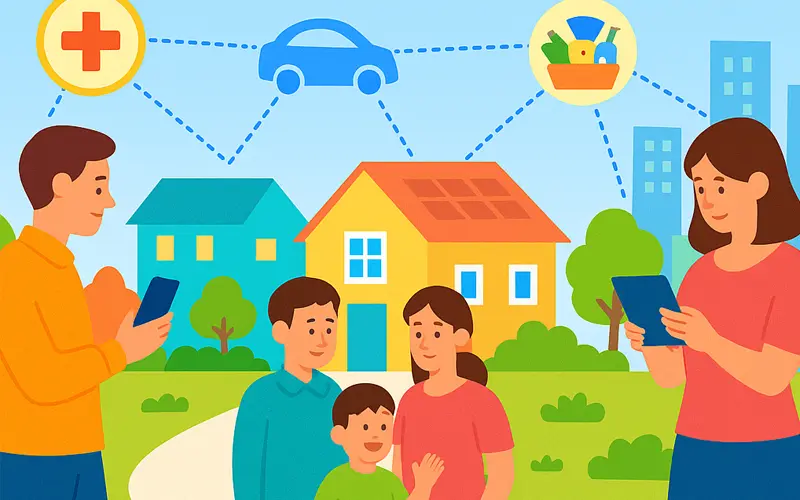
人と人のつながりが希薄になりやすい現代において、「地域のつながり」をどう再構築するかは大きな課題です。
高齢化や人口減少、災害リスクの増加といった問題を抱える地域では、ITやスマート技術を活用した新しいコミュニティづくりが注目されています。
Society5.0の考え方のもと、地域通貨やデジタル農業、地元SNSなど、地域の課題をテクノロジーの力で解決しようとする取り組みが各地で始まっています。
地域ポイントサービスで人と経済をつなぐ
まちのコイン(面白法人カヤック)
「ありがとう」の気持ちを地域内で可視化する、スマートフォンを使った地域ポイントサービス。地域活動(清掃・イベント参加など)に参加するとポイントがもらえ、地元のお店やサービスで使える仕組みです。単なる経済的インセンティブではなく、「つながり」そのものを価値に変える新しい形として注目されています。
地域の人との交流や協力が自然に生まれやすくなる/ボランティアや地域活動への参加が増え、地域に愛着を持つきっかけに。
せたがやPay(世田谷区)
地域経済の活性化を目的に導入された世田谷区独自のキャッシュレス決済サービス。利用者はポイント還元を受けながら、地元の商店街や中小企業で支払いが可能。キャンペーン連動で自治体と住民のコミュニケーションのきっかけにもなっています。
地域経済を身近に支援できる手段が増える/住民が地元で買い物をする動機づけになり、地域循環が強化される。
テクノロジーで農と都市をつなぐ
アグリノート(WARPS)
クラウド農業管理ツール「アグリノート」を活用した市民参加型農園の取り組み。農家がスマホやPCで作業データを共有し、都市住民も農業の工程や成長記録を「見える化」された情報として体験可能。農産物の購入や定期便契約にもつながるなど、都市と農業がデジタルでつながる新たなモデルになっています。
生産者と消費者の距離が縮まり、「誰がどう育てたか」を実感しながら食と関われる/地域の農業への理解・関心が高まる。
農業IoTプラットフォーム「Akisai」(富士通)
富士通の「Akisai(秋彩)」はクラウド型農業IoTプラットフォーム。農作物の生育状況や環境データ(温度、湿度、CO2濃度など)を可視化し、農家の栽培管理を支援。最近では都市部の飲食店や企業がこの情報をリアルタイムに共有し、ストーリー性のある食材提供に活用する動きも進んでいます。
消費者が産地・栽培環境を理解したうえで購入できる/都市部でも農業のリアルタイム情報が手に入る。
CSA(Community Supported Agriculture)× デジタル連携事例(全国各地)
CSA(地域支援型農業)は、市民が農家と直接契約し農産物を定期購入するモデル。これを支えるデジタルプラットフォーム(例:CSA cloud、食べチョクなど)により、収穫状況・配送予定・農家の声を簡単に共有。農家と消費者の双方向コミュニケーションが活発化する大きな動きが始まっています。
農家との距離感が縮まり、食品の安心感・信頼感が高まる/持続可能な農業の応援につながる意識が醸成される。
ご近所SNSで地域の交流を再起動
PIAZZA(ピアッツァ)
実名・住所ベースで登録できる地域限定SNS。子育て相談、地域イベント、防災情報の共有など、地元の人同士がつながるためのインフラとして注目。登録地域を越えた発信ができないため、安心感と信頼性が高く、トラブルも起きにくい設計になっています。
普段会わない近所の人とも自然につながる機会が生まれ、孤立感が減る/災害時や緊急時の情報共有にも役立つ。
Nextdoor(海外事例/一部国内展開中)
アメリカ発の地域SNS「Nextdoor」は、実名+住所認証型の近所限定SNS。掲示板・イベント情報・買い物支援・防犯情報の共有など幅広く活用され、地域住民の共助意識を高める場として機能。日本でも一部エリアで導入が進んでいます。
小さな助け合いや情報交換が自然に発生/地域防犯や災害対応力が高まる。
まちコミ(防災・見守り特化型SNS/行政連携事例)
まちコミは自治体や地域団体向けの防災・見守り特化型SNS。地域単位で登録者に向けて一斉通知、見守り活動、地域ニュースなどを発信。特に高齢者の見守り活動や災害時の情報共有に強みがあり、全国の自治体で採用が進んでいます。
高齢者や災害弱者も地域から孤立しにくくなる/行政と住民の信頼関係強化にも貢献。
技術が育てる“地域の絆”
スマート技術の活用は、地域社会に新たな活力をもたらしています。それは単に「便利になる」ことではなく、人と人の間にある温度や信頼、協力関係を再構築するための手段です。
このような取り組みは、地方都市だけでなく、都市部でも重要性を増しています。今後、地域をベースにしたスマートコミュニティのモデルが全国に広がることで、誰もが安心して関われる地域のあり方が見えてくるはずです。
まとめ:Society5.0の未来と私たちの生活

超スマート社会「Society5.0」が目指す世界は、決して「未来の特別な都市」だけの話ではありません。ご紹介してきたように、見守りサービスやスマート家電、地域のつながりづくりや防災支援など、多くの技術がすでに私たちの日常の中に入り始めています。
その本質は、「技術が先にありき」ではなく、一人ひとりの安心感や快適さ、地域とのつながりといった、人間らしい価値を高めていくことにあります。
離れて暮らす家族の健康や安全を見守ったり、移動や学びがもっと自由に、もっと楽しくなる選択肢が増えたり。地域の商店街や農家と都市の住民が、より身近な関係としてつながれる機会が増えてきたり。こうした変化は、誰にでも届くものとして着実に広がっています。
もちろん、Society5.0の実現にはまだ課題も残されています。
すべての人が公平にデジタル技術の恩恵を受けられるようにすること、地域ごとのニーズに合わせた活用法を見つけていくこと。
今後も試行錯誤が続くでしょう。しかし今、私たちができることはとてもシンプルです。「これは自分の生活や地域でも使えるかもしれない」と考えてみること。そして、自分なりに技術との距離を縮めていく意識を持つこと。Society5.0は、技術が人に寄り添う社会です。その未来は、すでに動き始めています。
これからも新しい取り組みやサービスに目を向けながら、誰もが安心して、自分らしく生きられる社会づくりに少しずつ関わっていきましょう。
※上記記事は2025年6月7日時点のものです。
※記事内で取り上げた商品・サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
※当サイトに掲載された情報については、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。



