気づけば部屋がモノであふれ、探し物が見つからない。
片付けなきゃと思いつつ、何から手をつけていいかわからない。
そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。整理収納は、ただ物を減らすだけでなく、暮らしを快適に、心を穏やかに整えるための大切なアクションです。特に最近では「おうち時間」が増えたことで、空間の使い方に目を向ける人が急増しています。とはいえ、一人ではなかなかうまく進まないことも。
この記事では、自分でできる整理収納の基本や手順、注意点を詳しく紹介するとともに、プロの整理収納アドバイザーに頼るべきケースや、信頼できる業者の選び方もあわせて解説していきます。理想の暮らしを実現するための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
家族で取り組む整理収納:日常に活かせる片付けの基本とコツ
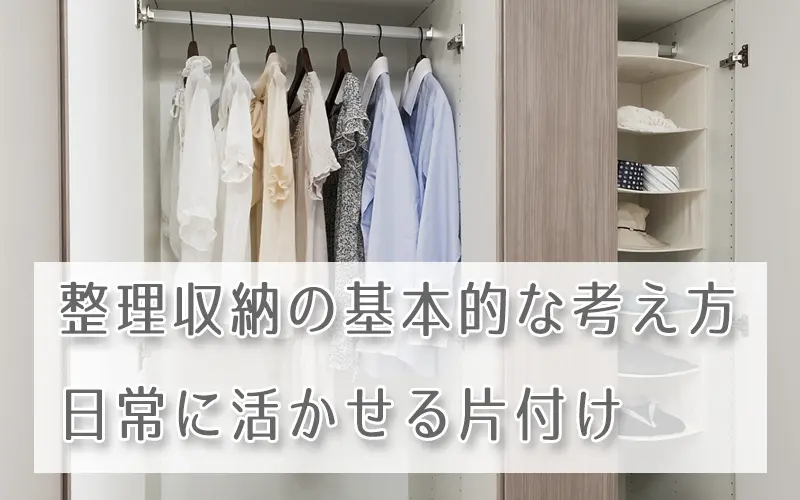
家の中をスッキリさせたいと思っても、なかなか手がつけられないのが「整理収納」。特に小さなお子さんがいる家庭や共働き家庭では、毎日の忙しさの中で片付けが後回しになってしまいがちです。この章では、家族みんなで取り組める整理収納の基本的な考え方と、実践手順、注意点をわかりやすく解説します。
整理と収納の違いを理解しよう
「整理」とは必要・不要を見極めてモノを減らすこと、「収納」とは使いやすく収めること。まずは整理から始めるのがコツです。
- 1.家の中の「気になる場所」を一カ所決める(例:玄関、キッチン)
- 2.中のものを全部出す
- 3.「使っているか」「今後使うか」で分ける
- 4.不要なものは手放す(捨てる・譲る・売る)
- 5.使う頻度と動線を意識して収納する
- 一気にやらず、1日15分でもOK
- 家族で「いる・いらない」を話し合う
- 子どもにも分かる分類方法(絵ラベルなど)を工夫
- 使用頻度の高いモノは腰目線の高さに
- 定位置を決めて、使ったら戻すルールを作る
- 「捨てられない」は感情の整理がカギ → 写真に残す・保留箱を使う
- 「収納が足りない」は詰め込み過ぎが原因 → モノの量を減らすことを優先
- 「家族が協力してくれない」は共有ルール作りから → 子どもも楽しめる仕組みを
整理収納は一度整えたら終わり、ではなく、暮らしの変化に応じて調整し続けるもの。次章では、整理収納サービスのプロに依頼する際の大切なポイントについてご紹介します。どんなタイミングで頼めばよいのか、どんなサービスがあるのか、そしてどんな点に注意して選べば良いかを詳しく見ていきましょう。
プロと一緒に解決!整理収納サービスの上手な使い方
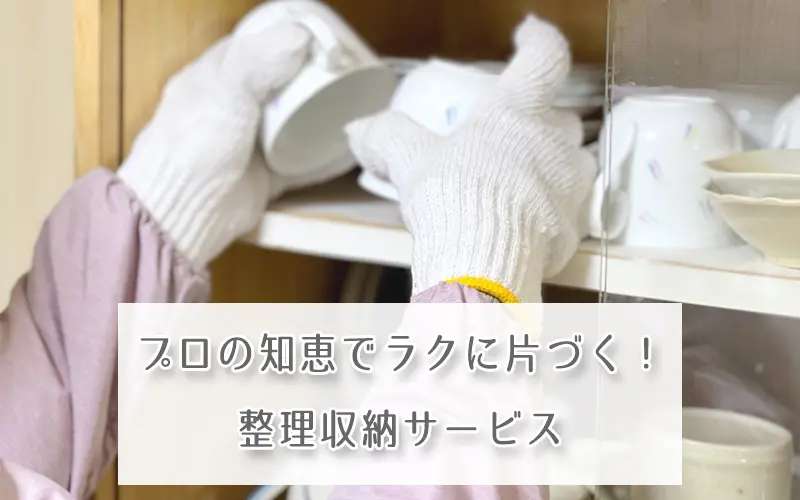
プロの整理収納サービスは、単なる片付けの代行ではなく、生活スタイルや家族構成に合った“使いやすい空間づくり”をサポートしてくれる心強い存在です。特に小さな子どもがいる家庭や共働き世帯では、時間的・精神的なゆとりを生み出すための頼れる選択肢にもなります。状況に応じて適切なタイミングで利用することで、整理収納の悩みを根本から解決することができるのです。
こんなときこそプロの出番!
「何度片付けてもリバウンドしてしまう」「そもそもどこから始めたらいいかわからない」―そんな悩みがあるなら、整理収納のプロの力を借りるのがベストです。客観的な視点で家の状況を見てもらえるため、無駄なく効果的なアドバイスが得られます。
整理収納サービスには何がある?
整理収納のプロは、単なる片付けだけでなく、「モノとの向き合い方」や「家族構成に応じた動線設計」など、暮らしを整えるための包括的なサポートを提供してくれます。サービス内容は、ヒアリング→仕分け→実作業→アフターフォローという流れが一般的です。
- 作業範囲(部屋単位/全体/収納内のみなど)
- 家族の同席が必要かどうか
- 所要時間とスケジュールの柔軟さ
- 実績・資格(整理収納アドバイザー1級など)
- 料金の透明性(時間単価/パック料金/交通費別など)
プロに任せるメリットとは?
自分だけで進めていた片付けでは行き詰まっていた場所も、プロの手が入ることで劇的に変わることがあります。プロは、単にモノを捨てる・収めるという枠を超えて、生活習慣や動線、家族の価値観に沿った“暮らしの最適化”を提案してくれます。また、心理的な背中押しにもなり、片付けに対する苦手意識が和らぐ効果もあります。
- 客観的かつ専門的な視点で収納設計してもらえる
- 自分では気づけなかった収納のクセや問題が見える
- 家族との関係性や動線に配慮した提案が受けられる
- 第三者が入ることで、片付けのモチベーションが一気に上がる
- 何より、時短・ストレス軽減につながる
整理収納のプロに依頼することは「他人に家を見せる」ハードルがありますが、それ以上に得られる安心感と暮らしの快適さは大きな魅力です。次章では、実際に依頼する際に比較検討したい業者情報を詳しくご紹介していきます。
整理収納サービス業者の比較と選び方
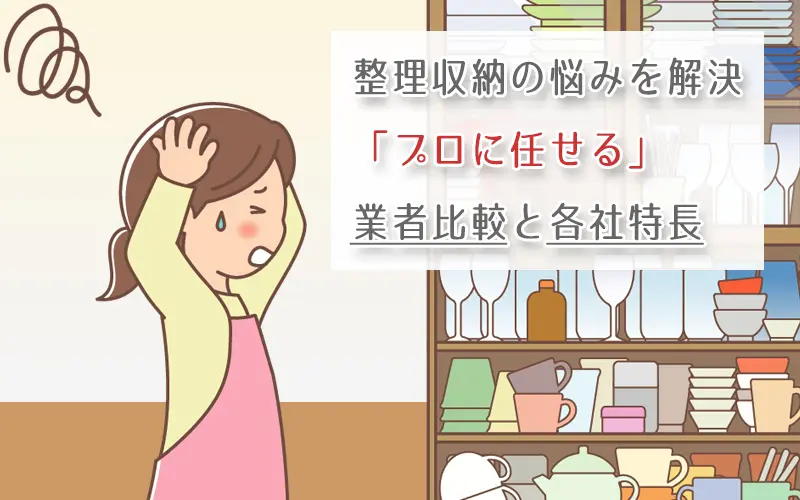
整理収納のプロに依頼する場合、「どの業者がいいのか?」と迷う方も多いはず。料金だけでなく、サービスの内容や対応エリア、スタッフの対応力など比較すべきポイントはたくさんあります。この章では、信頼できる整理収納サービス業者を選ぶための視点と、代表的な業者の特徴を紹介します。
- 提供サービスの範囲(部屋全体/キッチン/クローゼットなど)
- 料金体系(時間制/定額制/パックプランなど)
- スタッフの資格・スキル(整理収納アドバイザー資格の有無)
- 対応エリアと柔軟なスケジューリング
- アフターフォローの有無と対応力
どこに頼む?話題の整理収納業者とその特長
業者ごとに得意とするスタイルや対応エリア、サービスの柔軟性が異なります。料金やプランだけでなく、自分たちの暮らしに合った“サポートの質”を見極めることが大切です。ここでは、利用者から高評価を集めている注目の業者について、その強みや利用しやすさのポイントを詳しくご紹介します。
1.おうちデトックス
専門資格を持つスタッフが多数在籍。片付け×インテリアの視点から、理想の暮らしをトータルで提案。オンライン相談も対応しており、遠方からの依頼も可能。
2.ライフオーガナイザー協会(認定オーガナイザー)
ライフスタイルそのものを見直す提案が得意。考え方をベースにした「思考の整理」から始めるため、リバウンドが少ない。
3.くらしのマーケット
価格重視派に人気。個人業者とマッチングでき、口コミや実績を見て選べる自由度が魅力。ただし業者により対応力にばらつきあり。
4.ベアーズ
家事代行と整理収納がセットで依頼可能。子育て世帯に向けたプランや定期プランもあり、長期的な片付け習慣の構築に役立つ。
5.整理収納アドバイザー協会(ハウスキーピング協会)
認定アドバイザーを紹介するサービス。全国にネットワークがあり、要望に応じた人材を紹介してくれる。
家庭の状況別おすすめ業者
- 子育て中の家庭: ベアーズ、整理収納アドバイザー協会
- 費用を抑えたい方: くらしのマーケット
- 継続的な改善を求める方: ライフオーガナイザー協会
- 初めての依頼で不安な方: おうちデトックス
失敗しない整理収納サービス選びのために
業者選びは、見た目の価格や広告だけでは判断が難しいものです。実際に依頼してから「こんなはずじゃなかった」と後悔することもあります。だからこそ、事前にしっかりと情報を比較し、自分の希望や条件と照らし合わせておくことが大切です。以下に、よくある失敗例とその回避策を挙げておきます。
- 料金だけで選ぶとサービスの質が伴わないことも → 口コミや実績を必ず確認
- 見積もりが不明瞭なまま依頼 → 作業前に詳細確認&契約内容を文書化
- 依頼内容が曖昧 → 写真や間取り図で事前に状況共有を
利用者のリアルな声
- 「片付けのたびに夫婦げんかしていたのが嘘のように改善!」(30代・共働き)
- 「おもちゃ収納がうまくできず悩んでいたけど、子どもも進んで片付けるように」(40代・3児の母)
- 「引越し前に依頼して正解。無駄な荷物を減らせたし、引越し後も散らからない仕組みができた」(50代・単身)
整理収納サービスは目的や生活環境によってベストな選択肢が異なります。
まとめ:整理収納で叶える、家族の快適な暮らしと未来づくり
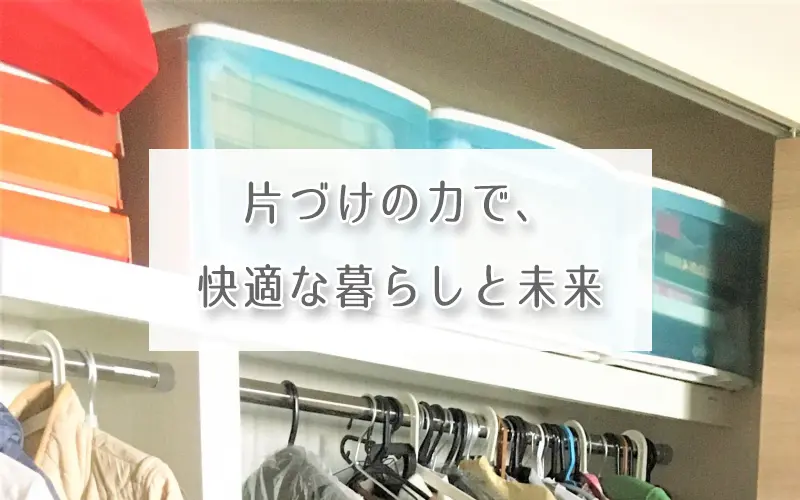
整理収納は、ただ「片付ける」だけではなく、家族の暮らしや心の余裕にも直結する大切な習慣です。自分たちでできる範囲をコツコツ進めることで、住まいが整うだけでなく、家族のコミュニケーションも自然と増えていきます。そして、どうしても手に負えない部分が出てきたときには、プロの整理収納サービスを上手に取り入れることで、悩みを早期に解決することができます。
片付けには「正解」はありません。家族のスタイルや生活のリズムに合わせて、無理のない方法を見つけることが何より大切です。今回の記事が、その第一歩を踏み出すきっかけとなり、あなたのご家庭に“ちょうどよく心地いい”整理収納習慣が根づいていくことを願っています。
散らかっていた空間が整ったときの清々しさは、何にも代えがたいものです。今日から少しずつ、自分たちに合った片付けを始めてみませんか?
※上記記事は2025年5月3日時点のものです。
※記事内で取り上げた商品・サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
※当サイトに掲載された情報については、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。



